Toon Boom日本支社は、Toon Boomのソフトウェアと日本のクリエイターたちの関係にフォーカスしたインタビューシリーズ『Toon Boom Interview Files』の連載をスタートします。第1弾となる今回は、2022年春にTOKYO MX、BS11で放送されたTVアニメ『ヒーラー・ガール』の原案・監督を務めた入江泰浩氏のインタビューをお届けします。 入江氏が、「今作の肝であるミュージカルシーンの実現に大いに役立った」と語るように、彼の制作に欠かせないツールだった絵コンテソフトStoryboard Pro。本記事では『ヒーラー・ガール』の事例からStoryboard Proの可能性についてお聞きしました。 続きを読む »
デジタルアニメ制作が、アニメーターの運命を左右するかもしれないという話。
アニメ制作のデジタル化には、わかりやすいメリットがいくつかあります。そして、その背後に分かりにくいけれども重要なメリットがいくつも隠れています。
今回は、Toon Boom日本支社の小口に、アニメ制作をデジタル化した際に生まれるメリットを『アニメーター解放宣言』という文章にして、寄稿してもらいました。デジタル化は、アニメーターにとって、そして業界全体にとって、何をもたらすのか?
アートのバックグラウンドを持つ小口ならではの視点からの分析をお楽しみください。
-----
アニメ制作において、誰もが直面する決定的な問いがある。
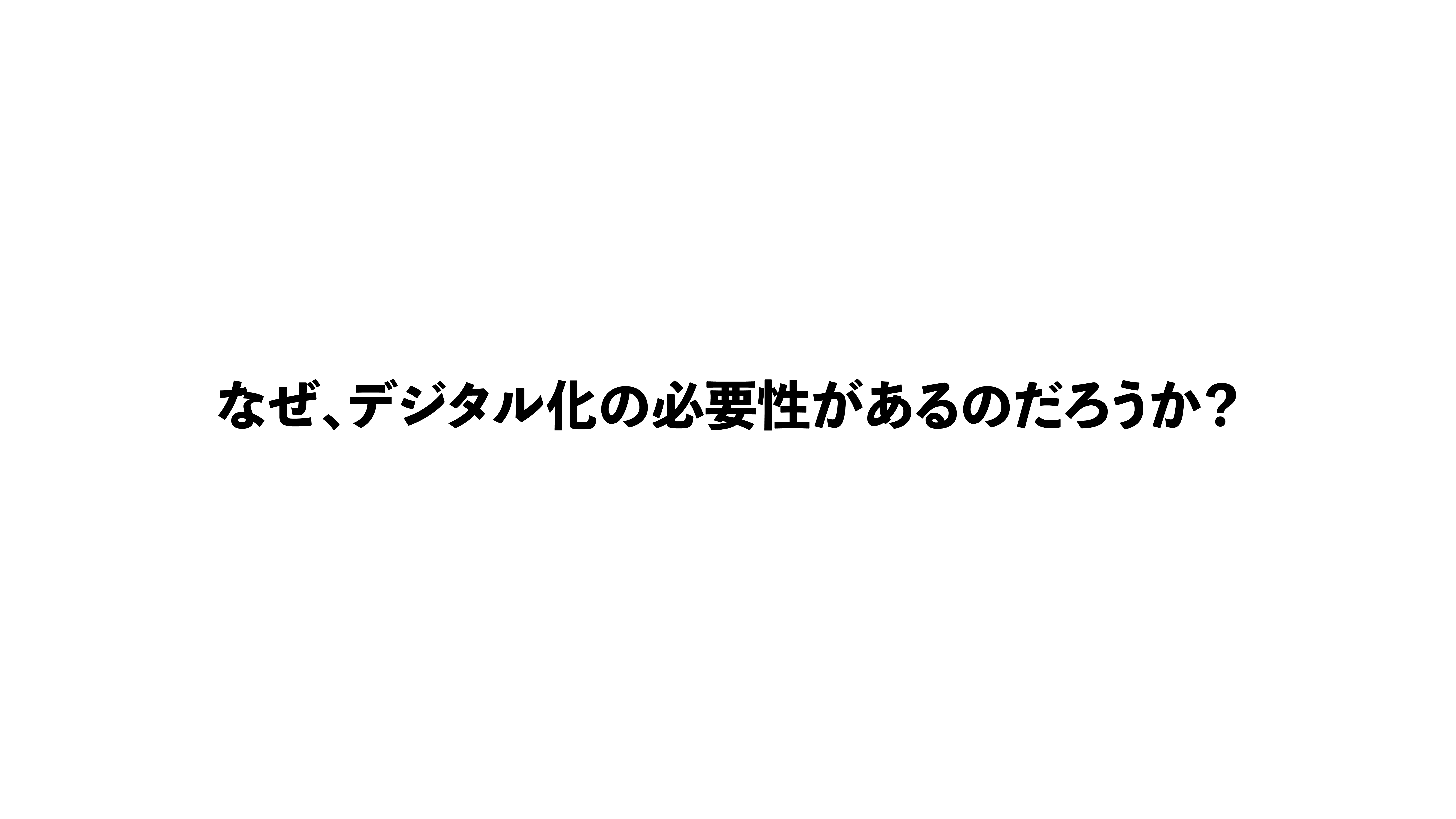
そのとき私たちの脳裏に瞬時に浮かびがるのは、例えば以下のような回答ではなかろうか。
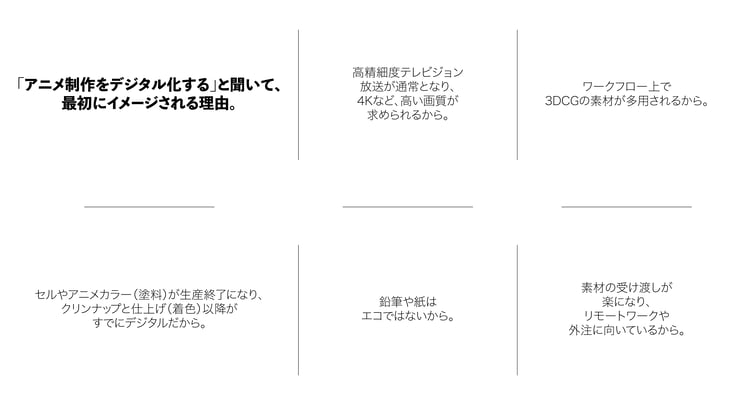
いずれの答えもデジタル化のメリットであることは間違いない。
しかし、ここでは、アニメ制作という小カテゴリーから一歩退いて、フル・スクラッチの映像作品の制作という意味において、いかにデジタル化が恩恵をもたらすかを考えてみたい。
なぜあえて「フル・スクラッチ」を冠したかというと、カメラで収集した素材をベースに切り貼りされる実写作品とは異なり、アニメーションはカメラに収めるべき素材から作っていく必要があるからだ。
日本画、漫画、絵コンテの関係
元来、日本の表象芸術において「枠」や「構図」という概念は非常に重要である。
「構図を取る」というふうに美術系の予備校や専門学校・美大では教わることになるのだが、平面であろうと立体であろうと、被写体をどのアングルで、どのスケールでフレーミングするかという作業が、完成作の良し悪しのすべて決定づけると考えられているといって過言ではない。
理由は様々考えられるわけだが、考えられるのは、日本人が音よりも、空間や時間に意味を込めることを優先するからであろう。漢字の1文字を分解してみればわかるように、漢字それぞれは象形文字を起源としているため初めから絵画的である。その絵画としての漢字は抽象され、線の数、角度、流れ、配置、空間の粗密などで構成されたデザインが意味を発生させる。さらに、それらが「へん」と「つくり」の複数の部分となり、組み合わさることによって、もう一つ高次元な、複雑かつ繊細な意味形成が可能になっている。ソ連の巨匠エイゼンシュテインは、漢字のこのような性質に注目し、複数の記号が寄り集まって弁証法的に生み出される別の意味に大きな可能性を見出していた。
「構図を取る」ことも同様だ。ここで、一枚の日本画を見てみよう。本作は太平洋戦争中の戦火に消えたものであるから実存はしない。筆者の個人蔵、昭和十八年「戦争美術展」画集からの抜粋である。

画面左側に零式戦闘機が見え、右のほうにはクロップされた何やら舞台のようなものが見える。よく見ると砲口がいくつか見えること、そして白い制服に身を包んだ人影が手を振っている様子から、戦闘機が艦上から飛び立ったシーンであることが理解できる。
描かれているものは少ない。しかし、充分にその様子が伝わってくる。それは構図の力にほかならない。
画面中央に大きく空間が空いていながらも、左側の零式戦闘機と艦上の水兵や物との関係は強い。いくつかの砲口の角度、水兵達の視線、そして吹き流しの角度は、すべて画面右下から左上に向かって放射状に延びる仮想のベクトルと一致する。むしろ中央と周囲の空間は、戦闘機と艦上の間に生まれる緊張感を下支えする、活性化された空間として、画面全体を引き締めている。
まるで、多くの戦友たちの視線に押されたカメラが左方向にパンしてゆき、雲ひとつない静謐な空に飛び立つ零式戦闘機と、その無垢さが捉えられているかのようだ。言葉なくして多くを語ることができるのが、構図の力である。
しかし、この「構図を取る」作業は、センスを問われる。どのような構図であれば表現したいことが、うまく、より効果的に伝えられるかという結論にたどり着くには天性の才能を持つ者以外は、トライ&エラーを繰り返す場数が必要だ。
それであれば、日本画のように一枚の構図に全てを賭すことをせずとも、前後の関係を元に、同様の操作が可能であるかを見ていくことにしよう。
例えば漫画のケースを見てみよう。
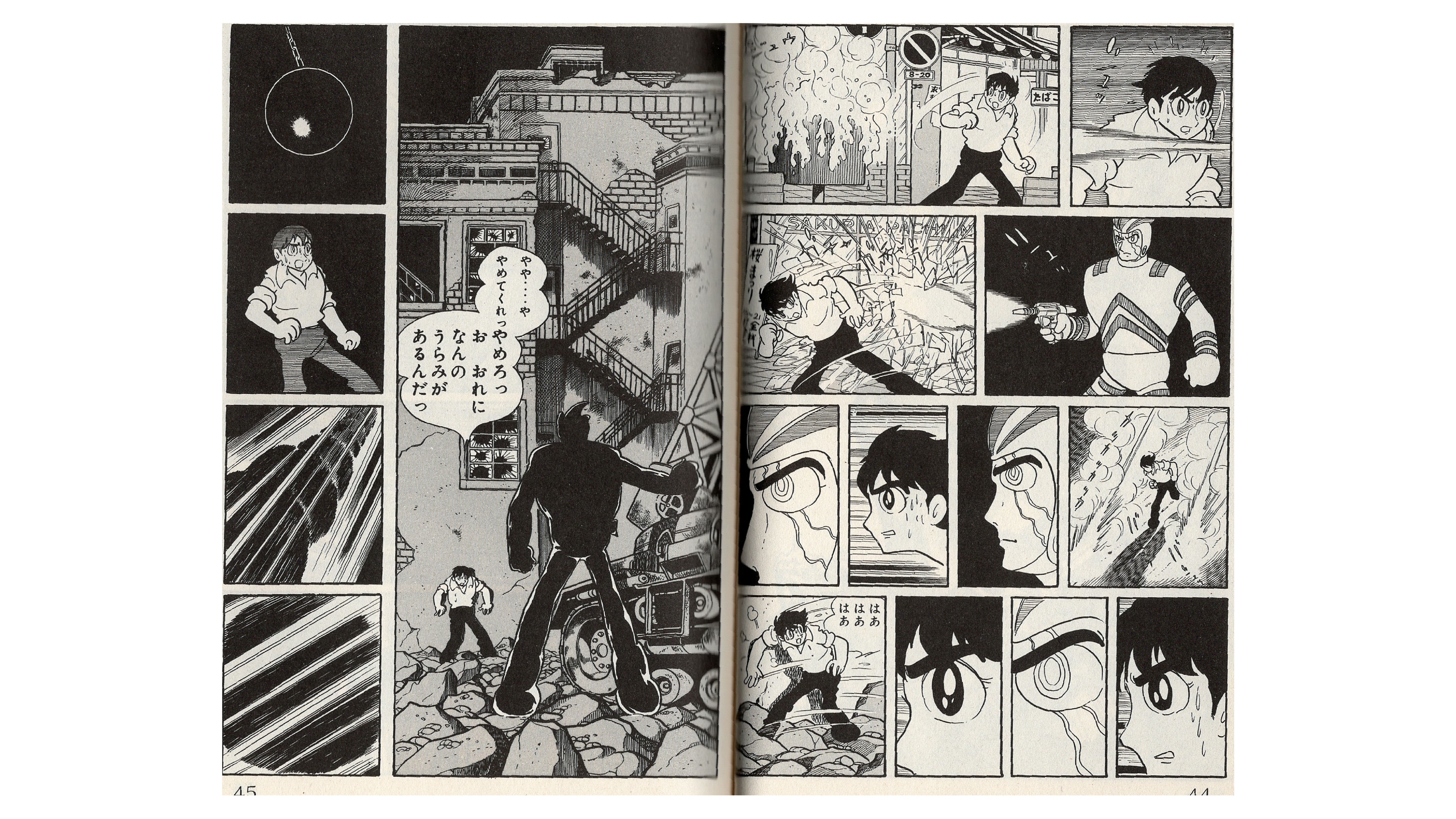
石森章太郎『幻魔大戦』より。©K.Hirai/K.Ishimori 1968
このシーンでは、ベガから逃げる東丈の心理がきめ細やかに、かつ効果的に描かれている。追われる東と、追うベガの横顔のショットがカットバックで交互に入れ替わり、次第にカメラが寄っていき、ベガが距離を詰めてきていることが表現されている。
次のショットでは、バックライトの効果で巨大で圧倒的なベガの体躯と、遠方に縮こまっている東の身体との対比が効果的だ。カメラは縦向きに置かれ、画面の上から押し寄せる重圧感と次の場面への期待が込められている。案の定、次の場面では上方に鉄球が、ストイックな漆黒の背景に浮かび上がり、ゆっくりと東に狙いを定めるようだ。
こうして、世界的に市民権を得ている大衆芸術「漫画」においても、日本の漫画家の手にかかると、映画制作に映像技術を駆使したレベルの画面構成が光っている。
絵コンテにおける「構図」
ここでやっとアニメに照準を合わせてみたい。絵コンテである。
絵コンテは、アニメ作品の「設計図」として非常に重要なわけだが、この漫画的な「枠取り」がそのままカメラワークとして生かされ、そこに秒数やフレーム数の時間軸が与えられ、同じ規格のカメラフレーム内に収められたようなものだと言うことができるだろう。
もちろん上記に加えて、効果音や台詞が手書きで記入されている。昨今の傾向では、絵コンテの構図はしっかりと取られているが、描写という意味ではかなり簡素に描かれており、演出がキャラクターの演技やタイミング、そしてカットの性格を判断しながら、レイアウト担当やその他の作業者に振り分ける工程が取られている。
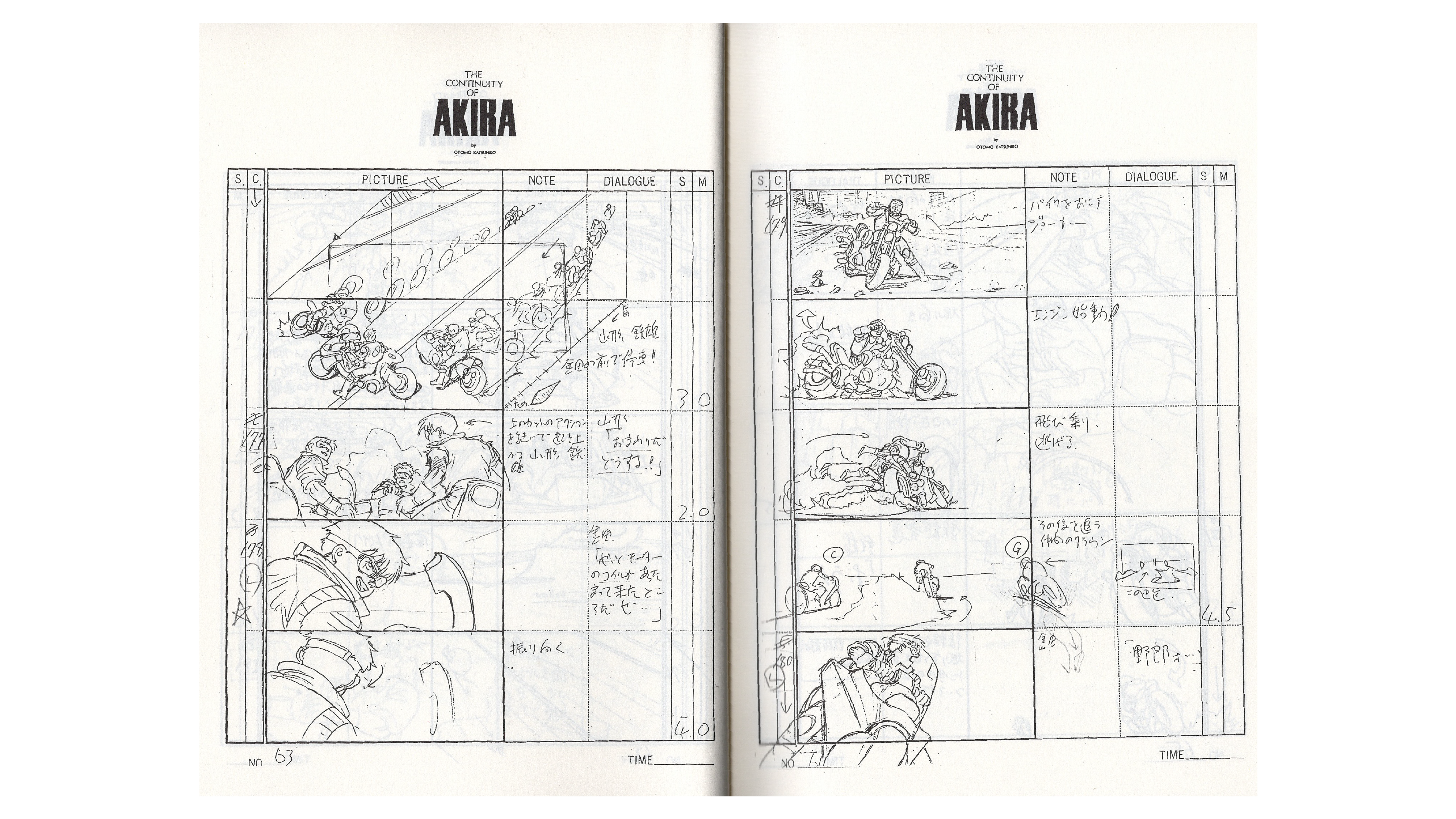
©1988 マッシュルーム/アキラ製作委員会
ここからの分担作業が、一つデジタル化の鍵となる。
演出は、レイアウト指示以外に、背景(BG)を描く美術へ発注する原図出しや、キャラクターの芝居のチェック、枚数や秒数のオーバーがありそうかなど、制作との打ち合わせで詰めてゆく。制作には、製作委員会や監督からのリテイクを絵コンテに反映させたり、場合によっては外注にコンテ撮を依頼してビデオ・コンテにしたりと、絵コンテを基準とした工程が相当数発生する。
しかも、その作業の内容を詳らかにしてみると、まず背景を描くのはPhotoshopであるから、絵コンテからレイアウトを起こし、画角の指定とブック分けの指示が必要だ。次にコンテ撮を行うには、社内であれば絵コンテをスキャンして、Premiereなどで連番に並べて編集して動画として書き出す必要があり、社外に発注すると、この作業に一週間かかった挙句、動画は納品されても、その間の連番画像は提供されなかったりする。
このことから明白なように、日本の「構図原理主義」とも呼べる構図/絵コンテ主導の制作には、関わる工程が日本画や漫画と比べて非常に多く、かつ常に修正要求に晒されてしまっている。
この絵コンテ主導の制作工程については、じつは宮崎駿監督は興味深いコメントを残している。
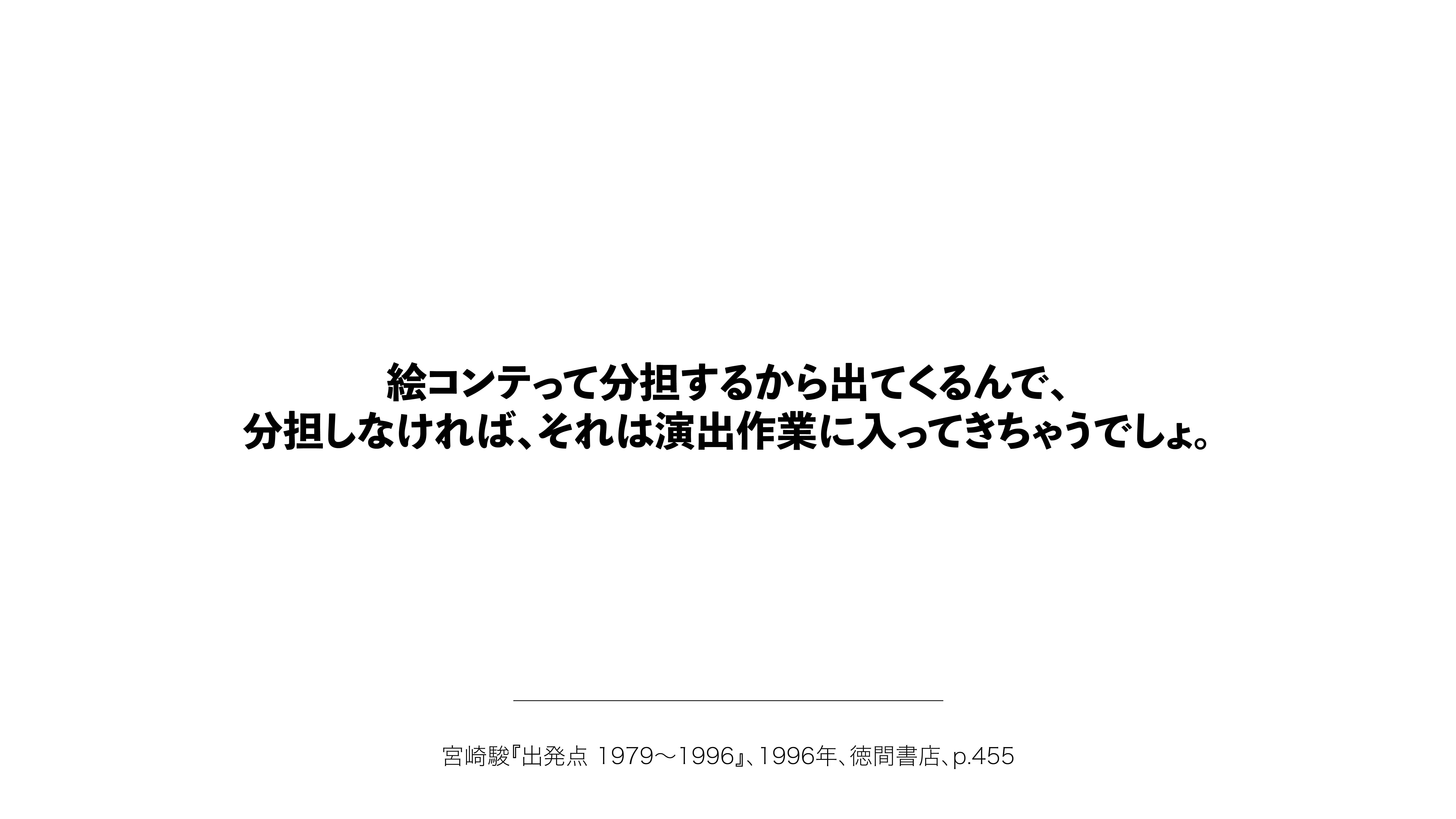
極論を言えば、アニメーターの頭の中で作品のすべてのイメージができあがっていれば、いきなりレイアウトや原画から始めても構わない。反対に、原作モノや大量生産が要求される作品においては、絵コンテは「設計図」という性格上、多くのスタッフと工程を経るため必要不可欠だが、その分、修正の回数も増え、人的ミスが生じるかもしれないという両面性を孕んでいる。
まさにこの点において、デジタルは強い。
ここまで、基本的な構図取りの重要性と、その工程に紐づくセンスや経験値が求められること、タイミングや演技のチェックと枚数判断の作業、そしてリテイクを含む、絵コンテから派生する様々な素材や工程の存在を明らかにしてきた。デジタルの素晴らしさは、これらすべてを、可塑的かつ進行形で行うことができることにある。
デジタルであれば、加筆・修正、タイミング調整、カメラワークの変更、画角の変更、3Dモデルの配置、ビデオ・コンテの書き出し、連番画像での書き出しなど、思いつくだけでも、これだけやれることが増える。
絵コンテ原理主義の考え方を取り払いさえすれば、絵コンテの段階で描き込みを増やしたり、CGや参考画像を取り込んだりして、より監督が考えるイメージに近づけてゆくことができ、そのままレイアウトとして機能し、原画作業へ入ってゆくこともできる。
若手アニメーターであれば、デジタル・ツールを駆使すれば構図取りやタイミングの練習になるし、オリジナル作品のアイデアであっても、普通なら自分以外に関わる人々の時間と労力をきにすることなく、自分一人で絵コンテからビデオ・コンテを書き出して、プロデューサーにピッチングすることだって可能だ。
私は、このクリエイター主体の柔軟性こそが、デジタル化の最大の強みだと信じてやまない。
万能なアニメーターとは ―― フレデリック・バックと宮崎駿
ここからは、Toon Boom本社があるモントリオールを活動拠点としていたフレデリック・バック(Frédéric Back)の作品を話のきっかけにしたい。
もしかすると海外のアニメーションに馴染みのある人でなくても、ジブリ美術館またはジブリ関係のイベントや展覧会でフレデリック・バックのことをご存知の方がいるかもしれない。このカナダが誇るアニメーションの巨匠バックは、アカデミー賞の短編アニメーション部門で二度もオスカーを受賞している。

© Frédéric Back/ Société Radio-Canada
その一つに『CRAC!』(クラック!)という作品がある。この作品の独特な自然の描写とその手法を見て、宮崎駿はショックを受けたと言い、下記のように述べている。
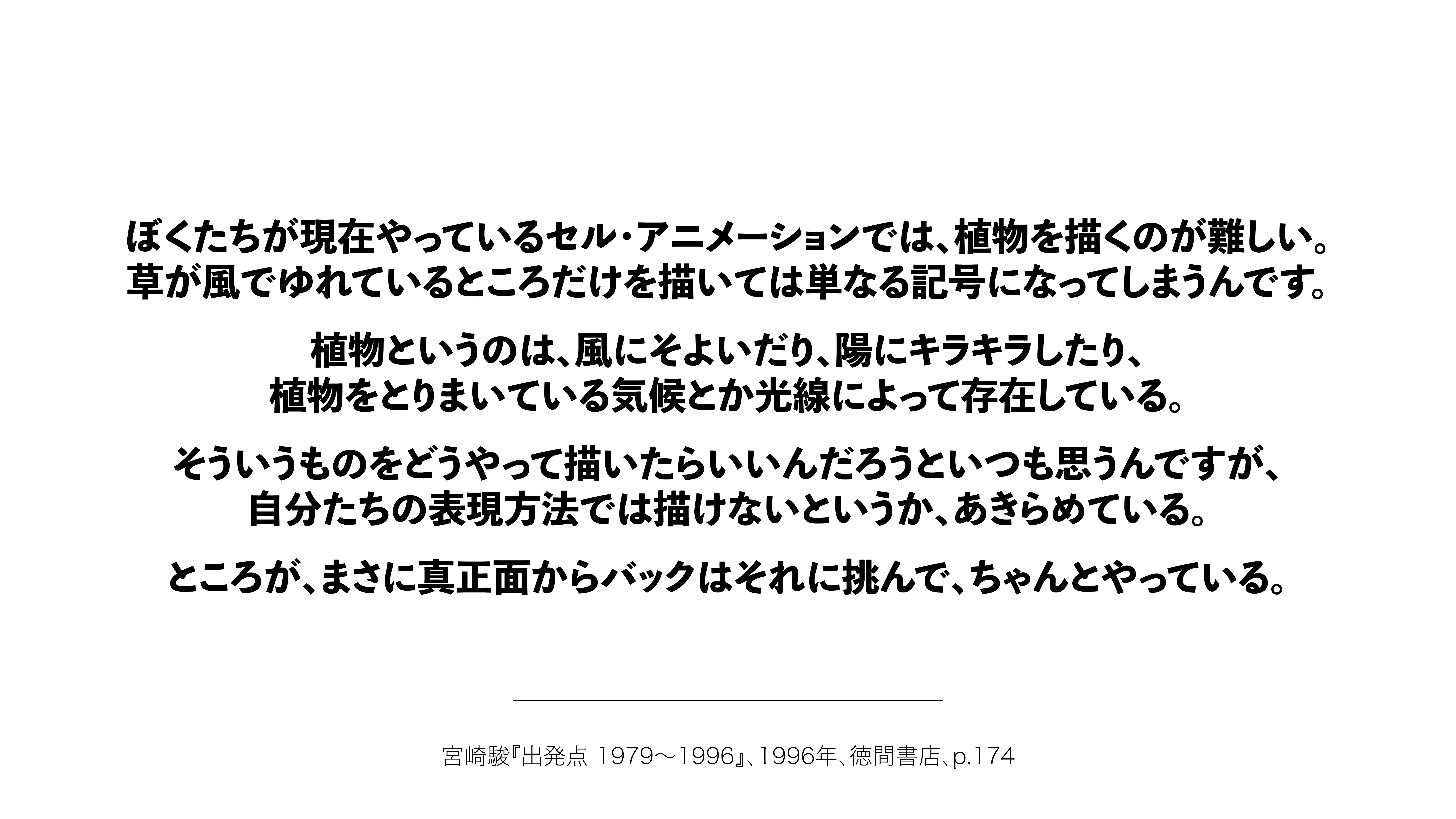
「自然」はいったいどのように表現できるのだろう。少なくとも、当時の本人が自ら認めるところでは、宮崎が描く自然は、木が揺れる、草が風でそよぐといった、記号としての表現に限定されている。日本のセル・アニメーションは記号による表現を主体としている。記号とは、ある特定の共有された意味が伝達される媒体だ。
バックの作品を見てみると、登場人物や背景の描写には、固執した様式がない。人、家畜、鳥、蝶、風、雪、それぞれが全く異なるタッチで描かれていて、背景のレイヤーとの関係性や異なる撮影技術によって語られている。日本のアニメが通常とするところの閉じた輪郭線やムラのない色面という文法はここには存在しない。バックは、自らが自然と向き合って感じたままのセンセーションを表現することに成功している。
同書で、宮崎はアニメーター像を下記のように捉えていた。
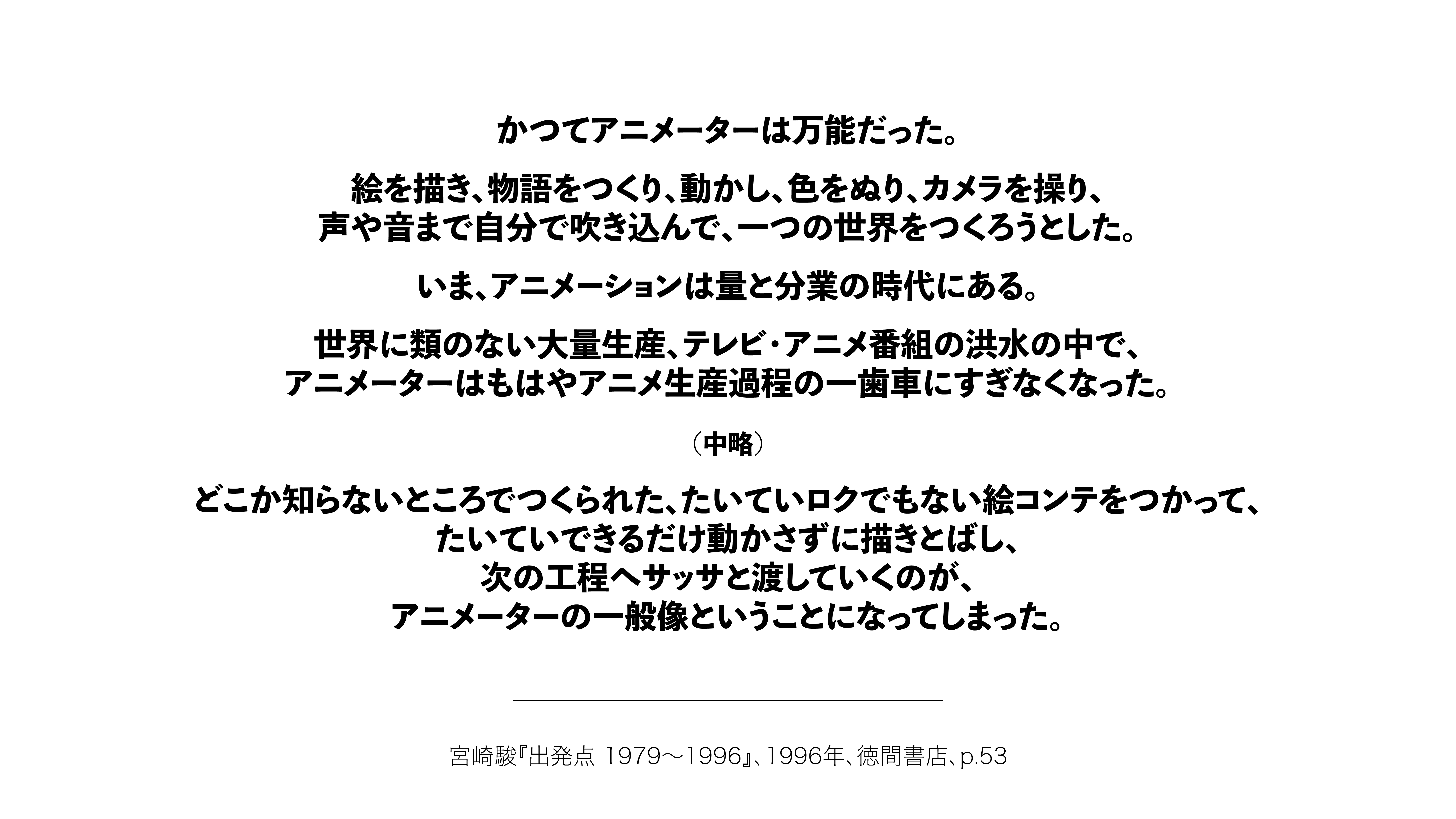
続けて宮崎は、このようにも話している。
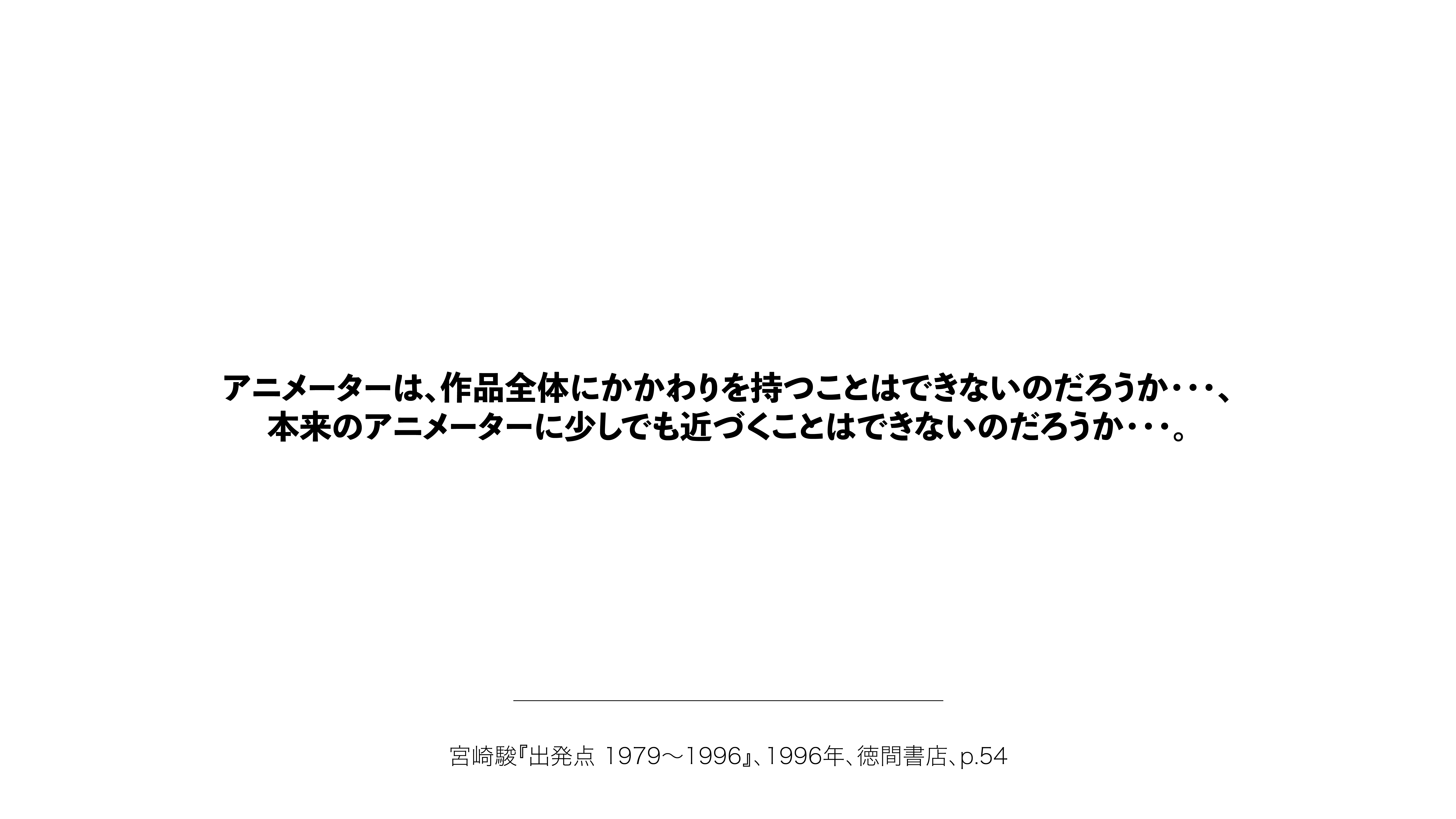
この文脈から読み取れることとして、宮崎がバックの作品に見出しているのは、単独のアニメーターの万能さと自由度であろう。自然をうまく描写することは、それぞれのエレメントをそれぞれ異なる手法によって描写できる自由度であり、それが成立するのは、アニメーションの制作工程すべてをアニメーター自らがこなせるという万能さが光るからだ。
筆者はここで、デジタル化が、宮崎の言う本来のアニメーター像を生み出せると言っているわけではない。確かに、現代のソフトウェアがあれば、こうした個人制作のアニメーションはバックの時代よりもはるかに低リスクで創造できるだろう。しかし、現実的に言って、私たちのアニメ業界は、大量生産を日々こなしていくのに精一杯だ。
ここで宮崎は、分業化されたアニメ制作においても、アニメーターは自分の個性や表現を世に出すことができると言う。
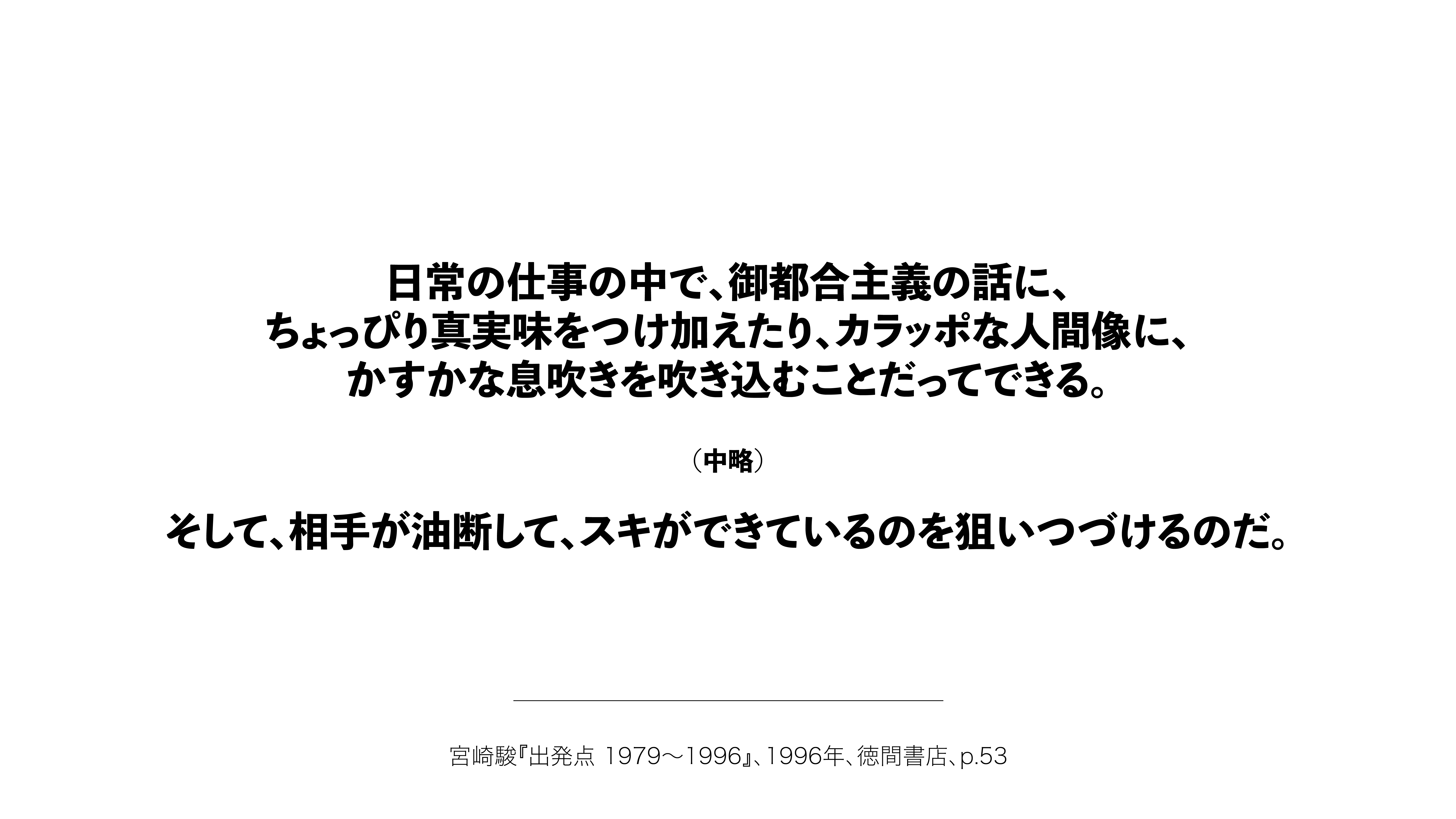
アニメーターの個性をいかに出すか。そして、課題は彼らがいかにスキを見つけ自分たちの表現を突き通すかということになる。逆説的ではあるが、歴史的に、分業・大量生産主義のアニメ制作の均質化された制度が生きることになった。
大量生産主義のアニメ制作では、作画監督システムの導入で、線に統一化されたクオリティを持たせたアウトラインで囲まれた描画が一般となり、色面に関しても、セルの裏側からアニメカラーを使って着色されるため、色ムラや抑揚が限りなく抑えられる。現在の「にわかデジタル化」したクリンナップと着色のプロセスも、昔の手法と根本的には変わっていない。
しかし、予算・時間・人手不足が蔓延している制作現場にあって、こうした描画の均質化による大量生産の安定化の狙いとその制作の統率力の弱さを逆手に取り、一部のアニメーター達は演出の意図をうまくはみ出し、自らの独自の表現をTVスクリーンに表示し続けた。
70年代後半〜80年代に黎明期を迎えるエフェクト作画や極度にデフォルメされたアクション作画の領域において、あるトレンドを引き起こすことになる、金田伊功とそのフォロワーたち。思いつくところでも、山下将仁、板野一郎、庵野秀明、大張正己など、枚挙にいとまがない。

(左)『BIRTH』(1984)、(c)ビクター音楽産業株式会社 / (右)『幻魔大戦』(1983)、(c)角川映画
その結果、彼らが発明したエフェクト作画や極端なデフォルメがアニメ表現のボキャブラリーに加わり、マニアックなアニメ・ファンたちに注目されるようになる。今では日本のアニメのアクション・カットには、国内外問わず多くのファンが存在する。
これまで、アニメーター像というものを下記の二つの切り口で捉えてみた。

コミュニケーションとしてのデジタル技術
先述の繰り返しになるが、強いアウトラインの線に囲まれたキャラクターを動かすアニメーションは、あくまでもアニメが大量生産されなければならない状況における、一つの解である。輪郭を持たせるということは、物事のあり様を定義づけることになり、その領域の内側には、いかなる読解の誤差をも挟ませない。
キャラクターの描写とそれらの演技を次の工程に手渡すには、ディテールが省略化(記号化)またはデフォルメされているほうが伝わりやすく、線を引く担当者や色を塗る担当者の作業がしやすくなる。
そのためアニメーターの作業領域は狭まる。現代のアニメーターは、受け取ったカットを指示された通りに作業し、制作に渡し、演出や作画監督チェックをスムーズに通過することが一つの評価点となる。
さらに遡って演出の段階で、このカットは喋りメインだから止め絵でいいとか、カメラで寄ったり多段スライドしたりと、撮影でなんとかするから、という省エネ演出の判断が下されると、そのカットを受け取るアニメーターはさらに文脈を喪失し、想像力を働かせられる部分が削ぎ落とされてしまう。
これは何を意味しているのか。
まず言えることは、制作と演出そしてアニメーターの間に、複雑なコミュニケーションのネットワークが存在しているということだろう。
自分の前の工程からの指示は何を意味しているのか。自分の後ろの工程には、どのように手渡せば良いかなど、大量生産の現場にあって、制作デスクという接点があったとしても、アニメーターは、連続する全体像を想像力の内に捉えることが要求されている。
その際、絵コンテ通りレイアウトを切って、そのまま従って原画を描き、原画の線のクオリティを維持してクリンナップするなど、アニメーターたちのスタンスは従順にならざるを得ない。リテイクや修正指示が入って戻されると、時間がロスしてしまうし、次から仕事をもらえないかもしれないからだ。
この状態で「演出の意図をはみ出す」ことはリスク以外のなにものでもない。演出と制作そしてアニメーターの間に存在するコミュニケーションのエコシステムは、お互いを尊重しつつ、繊細な承認のプロセスの上に成り立っている。
ただし、それは紙で作業をしているからだと言えないだろうか。
デジタルであれば、線のクオリティや演技の情感、デフォルメの強度など、カットを自分なりに解釈した視覚的表現を演出に提案し、仮に突き返されたとしても、すぐに修正し、再提案することができる。すぐにコミュニケーションできれば、制作にかかる負担も減るだろう。
デジタル化はなにも、高画質のためとか、CGとの相性が良いとか、すでに動画・仕上げ以降がデジタルだからという環境論だけに落ち着くものではない。デジタル化は、監督や演出を含むアニメーターだけでなく、制作やプロデューサーにとっても、日本から発信されるアニメ作品がより良いものになるための、大きなポテンシャルを持った、技術なのである。
ここで筆者が技術と述べたことには理由がある。現在のアニメは常に進化している。アニメは日本が世界に誇る一大クリエイティブ産業に成長した。それは、先人たちの礎の上に安住の地を見出すのではなく、現在のアニメーターたちが、さらなる高みを目指しているからにほかならない。デジタル化は、足枷ではなく、翼なのである。
最後に宮崎駿の言葉を引用しつつ、筆を置きたい。
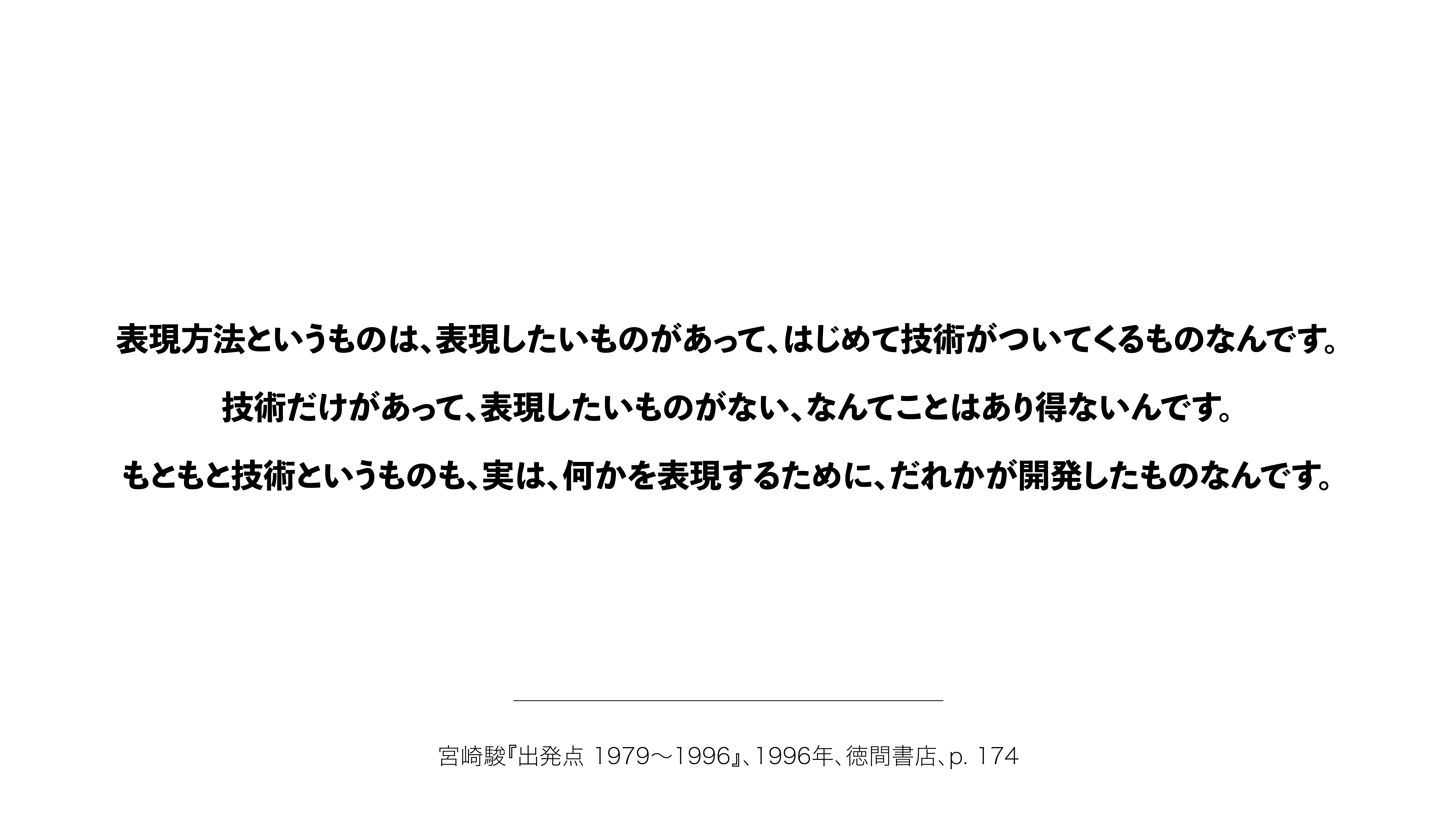
-----
読んでいただきありがとうございます!改めて、Toon Boomの小口と申します。
Toon Boom製品に関するご質問や、情報交換をご希望の方は、気軽にお声掛けください。hoguchi[at]toonboom.co.jp (ご連絡いただく際は[at]を@に変換してください)


